オークの森から生まれた『ブッシュ・ド・ノエル』

オークの森と巨木崇拝
紀元前7,000年頃 中央ヨーロッパからスカンジナビア地域は、現代ドイツ語でアイヒェ die Eiche、英語でオークoak と総称されるブナ科コナラ属に属する喬木やヨーロッパブナが育ち、その足元にヘーゼルナッツを実らせるハシバミなどの低木が生育して、しだいに深い森になっていきました。


そんな中石器時代 人々は狩猟に加え、森に入ってオークの木が落とすどんぐりを拾い、ハシバミの木からヘーゼルナッツを採集して、それら木の実を主食として暮らしていたと考えられています。
*木の実は「人の命を養うもの」その木の実をたっぷりもたらしてくれる森の巨木は生命を託す「生命の木」として崇められ、神格化されていったのです。
ゲルマン人と精霊信仰
前5~4世紀 こうした森が形成された南スウェーデン,デンマーク半島,北部ドイツに広がるバルト海を囲む地域に居住していた人々をゲルマン人と呼びます。
北ゲルマン地域には デーン人やノルマン人
西ゲルマンには アングル人、サクソン人、フランク人、アラマン人など
東ゲルマンには東ゴート人,西ゴート人,バンダル人,ブルグント人、ランゴバルト人など諸部族が暮らしていました。
それらのゲルマン民族が持っていた信仰は、自然界のあらゆる事物には、霊魂や精霊が宿り、諸現象はその意思や働きによるものとみなす多神教的な精霊信仰であり、自然崇拝の1つとして森の中の大きな木を神木として崇める『巨木崇拝』がありました。
そして古代ゲルマン人は古代日本人と同じく、霊魂の不滅を信じ、祖先の霊を守り神として祀って暮らしていたのです。
ゲルマン人の大移動
376年 西ゴート人がドナウ川を越えて移動を始め、568年北イタリアでランゴバルト王国が建国されるまでを第1次ゲルマン人大移動 次いで8世紀に始まり11世紀まで続いたノルマン人の移動を第2次ゲルマン人大移動といいます。
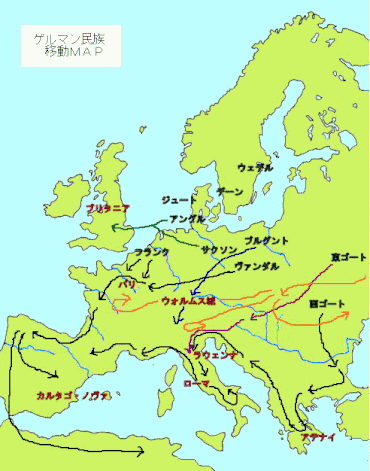
ゲルマン民族が次々とローマ帝国内に侵入し、国家を興すと、ヨーロッパは混乱状態に陥り、395年ローマ帝国が東西に分裂します。その後多くのゲルマン系国家は、東ローマ帝国やイスラム勢力、唯一生き残ったフランク王国に征服されていくのですが、フランク王国は西ヨーロッパで数世紀にわたって勢力を強め、領土を拡大 5世紀末の建国初期からローマカトリック教会と関係を深めていきました。
ローマ帝国内に移動し、住み着いたゲルマン人たちは次第にローマ人との同化が進み、キリスト教を受け入れていったと考えられますが、現在の北ドイツや北欧諸国エリアで暮らすゲルマンの人々は9世紀になっても古来の自然崇拝、精霊信仰を持ち続けていました。
消えない自然崇拝
『ワイルドハントWild Hunt』は9世紀頃から14世紀にかけてゲルマンの人々に信じられていた伝承で、10月末から冬至にかけて太陽の力が最も弱くなる頃 長い暗闇の中で雪嵐に怯えながら激しく厳しい自然現象をゲルマン神話の神オーディンやトールの行いに重ねたものです。
厚い雲が陽光を遮り、強風に煽られた雪が荒れ狂う冬の嵐は、オーディンが8本足の軍馬スレイプニルに跨り狩猟道具を携え、猟犬や猟師たちを引き連れて空や大地を大挙して移動していくさまと考えられました。神に従う猟師たちは死と関わる妖精、亡霊や精霊、悪魔などで、この狩猟団を目にすると戦争や疫病といった大きな災いを呼び込むと考えられ、目撃した者は死を免れないと恐れられていましたから、人々はワイルドハントが過ぎ去るまで家に閉じこもって過ごしたといいます。

またノルウェーでは亡くなった人々の魂が空を駆け抜けて、土地を肥沃にしてくれるガンドライド「魂の騎乗」が信じられ、このガンドライドは、冬至から年明けの頃最も盛んになるとされていました。
『ユール』
古代の人々にとって冬至に向かう日々は生命の象徴である太陽の力が日に日に弱くなるため、不安と恐怖で過ごす期間でした。人々は太陽の再生を祈る一方その日を界に再び力を増す太陽を神聖で貴重なものと崇め、冬至の日から新な年が始まると考えるようになります。
こうして太陽の再生を祝い、前年の収穫と一年の無事を神に感謝し、来る年の豊穣と家内安全を願った冬至の祝祭が『ユール』です。この時期は死後の世界との扉が開き、先祖の霊が戻ってくると考えられており、宴席には亡くなった祖先の霊も参加すると信じられていました。
『ボンファイヤー』
キリスト教化が進む中でもゲルマンの人々はユールを祝い続け、冬至に向かう頃暗闇や寒さと戦う太陽のために薪を積み上げ、火を焚いてその復活を祈りました。
親族や集落の人々が集まり、冬至の焚き火『ボンファイア』の周りで歌って踊り、神への供物とした豚を食べ、ビールを飲む宴会が連日続けられたのです。ボンファイアは絶やしてはいけない神聖な灯火で、祭りは冬至から年明けまで続きました。
『ユールログ』
古来ボンファイヤーに使う焚き木の中で、最も太くて立派な焚き木は特別『ユールログ』と呼ばれ、リボンを付けて飾られて、冬至の日に新年の家内安全と豊穣を託して薪にくべられました。その薪には魔力があり、燃える火は太陽の再生を助けるとともに、この季節祖先の霊と共にこの世に入り込む悪霊や悪魔から守ってくれる。反面この火に影が映らなければ、災いを免れず、死の予兆であるともいわれ、畏敬の念をもたれていたといいます。
その灰はあらゆる病の治療薬に使われ、雷避けに暖炉にくべられ、飼葉に入れると牛が安産となり、畑にまくと豊作に、井戸に入れると水の味が良くなるなど、様々なご利益をもたらしてくれるものとして一年間大切に使われました。
キリスト教との融合
キリスト教の布教が進む中、ゲルマンの人々が冬至を迎えるにあたり、先祖伝来のユールログを崇め、ボンファイアを灯す習慣は衰えるどころか盛んになっていったものですから、キリスト教会はその異教の風習に手を焼き、やっきになって阻止にかかりました。6世紀キリスト教会が発布した禁令の文書が残り、以後迷信だとして弾劾、禁止し続けるのですが、そんな指導禁令はものともせずゲルマンの人々はユールログを崇め、ボンファイアを灯し続けたのです。
とはいえ、冬至の日を挟んで存在した祝祭『ユール』は時の流れの中でキリスト教のクリスマスに吸収され、ユールログ を火に焚べるのもクリスマスの12月25日に移動してゆきます。
そして屋外での焚き火は屋内の暖炉にかわり、巨木は枝葉を落とされ、丸太にされて家へと運び込まれるように…
そんな変化があったとはいえ、人々のユールログ に傾ける信仰と情熱はかわらず、
切り倒すに当たって代々伝わるお決まりの祈祷文を詠い、家族の最年長者や最年少者が薪に乗って、祈りをささげたり、薪を家に運び入れる際には、ワインや穀物を振り掛け、常緑樹の葉やリボンで飾ったり、燃やす前にはチョークで人形を描いたり…
ユールログ を暖炉に運ぶ人々 ロバート・ヘリック 1591-1674 イギリス

森からログを運ぶ家族 1832年 ドイツ

オートプロヴァンスのユール ログの儀式 19 世紀末 フランス

この習慣はヨーロッパ全域に広がり、薪を取る木は、スコットランドではカバノキ、フランスプロバンスでは果樹、セルビアなどバルカン半島の国々ではオークやオリーブやブナ、東ヨーロッパのスラブ民族の国々ではトウヒなど身近な樹木が使われました。
ここで現代フランスの食の専門家マグロンヌ・トゥーサン=サマ氏が著書『お菓子の歴史』(河出書房新社)内で著されている過ぎし日フランスの家庭で行われていた「冬至のお祭りに家庭の暖炉でほんものの木の薪に厳かに火をつける伝統」をご紹介しましょう。
『一般に、3日間、7日間、12日間(象徴的に重要な数字)と、昼夜をとおして燃やすための果樹の幹や大きな枝は、家庭のかまどで、家族の中でいちばん年長の者といちばん若い者が神妙に火をつける。火をつける前にしばしば、暖炉の床にオイルや蜂蜜やワインやミルクや聖水がまかれる。この陽気な日の儀式には、正しい人の守るべき義務がすべて含まれている。火を崇め、祖先を大切にし、風習を絶やさないことである。』
こうして『ユールログ』を崇め、飾って、クリスマスの夜 薪にくべる習慣は19世紀に最盛期を迎えています。
しかしながら、その後しだいに忘れ去られていくことに…原因として木材の減少や森林法などにより伐採規制が強化されたため、さらに20世紀に入ると一般家庭でもセントラルヒーティングが導入されるようになり、暖炉が使われなくなったことがあげられます。
ブッシュ・ド・ノエルの誕生
19世紀末 フランスのパティシエがこのユールログ を模して『ブッシュ・ド・ノエル』を考案
…ブッシュは「薪」、ノエルは「クリスマス」を意味し、クリスマスの薪:『ブッシュ・ド・ノエル』は話題を集め、瞬く間にクリスマスケーキを代表する1つとなったということです。

ゲルマン人の心のふるさととも言えるオークの森で育まれた巨木信仰 そこでDNAに刻み込まれた…といっても過言ではいユールログ はケーキとしてこれからも継承され語り継がれるに違いありません。
☆キリスト教は3世紀からゲルマン諸族に伝道を行い、改宗させる過程で、ゲルマン人の古来の信仰を捨てさせていきます。その過程では、手荒な実力行使も行われ、史実として語り継がれています。
そんな昔語りの1つイングランド出身の宣教師ボニフェティウスが723年当時まだ深い森が広がっていた 現在のドイツ ヘッセン州北部のフリッツラーFritzlar近郊のガイスマル Geismarという小さな村で行った布教の様子を『ゲルマン信仰とキリスト教』でご紹介しています。
